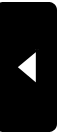下仁田納豆南都さん編
2018年12月08日
下仁田納豆の創業は昭和38年。
南都さんの父親が、
回り道をしながらも家族10人を養っていくための手段として
「納豆屋」を始めた。

当時は造った納豆を売り歩く、
引き売りの納豆屋だった。
「なっとぉ、なっとぉ~~♪」と売り歩く
父の姿の頼もしさは、当たり前でもあり、
思春期を経て、少しづつ
「自分はもっと大きな仕事がしたい。」
そう考えるようになっていったという。
高専を卒業し社会に出て、
設計エンジニアとして働くことになった。
社会に出て都会での生活は
何かをすり減らしていくようだった。
そして、時々思い出す父親の作る納豆が
懐かしくも、美味しくも感じるようになってきた。
そんな時、突然、父が家族に廃業を告げた。
「苦しいながらもなんとか子供達が育ってくれた。
これでもう納豆屋には未練がない。」
何かにこだわって
造ってきたわけではないだろうが、
それでもおいしい父親の納豆。
それ以上考えることもないまま、
自分の居場所を探すように「継がせてほしい。」と
自然に結論を出していた。
父、母、自分の3人が食べていけるように、
引き売りからスーパーへの卸を
増やしていくことを考えた。
電話帳を片手に片っ端から営業を掛けた。
ほとんど、すべてのスーパーで断られた。
その理由はすべて「値段が高い。」ということだった。
納豆業界もオートメーション化が進んでいた。
炭火を使って発酵させる。
寝ずに番をして造る納豆は
当然価格では太刀打ちできない。
絶望の中、それでも価格を合わせるか、
首をつる覚悟で考えていた。
そんな時に救いの神が現れた。
もぎ豆腐店の茂木稔社長との出会いだ。
値段よりも品質に興味を持ってくれた。
そして初めて試食をしてくれた。
「なかなかいい。どんな大豆を使っているか?」
原材料を聞かれた。
「大豆は一番安いものを問屋から買っている。
国産か外国産かも分からない。
でも、技術があるから、
うちの納豆はおいしいと言ってもらっている。」
と答えた。
当時の南都さんは素材など興味がなかった。
生きるために造ってきた納豆を
如何にして売っていくか。
商売とはそういうものだと理解していた。
茂木社長は言う。

「食べるもののおいしさは
素材の良さを引き出してこそ。
素材7割、製法3割だ。
いい素材で造れ。全部買ってやる。」
すべてのフレーズに衝撃を受けた。
「この人に付いていくしかない!」
素直にそう思った。
茂木社長に買ってもらえるように、
いい素材で造った。

そして、
本当に全部買ってもらえるようになった。
ただの納豆屋から、
「本当にいい納豆とは」という命題を持つ
本物の納豆屋へ変革していくための
衝撃的な教えだった。
さらにドラマは続く。
一年して、
茂木社長から取引の停止を言い渡された。
理由は「君は努力を何もしていない。」
と言うことだった。
まったく意味が理解できないまま、
茂木社長に詰め寄った。
「取引を停止されたら売り先がない。
店がつぶれてしまう。なんとかしてほしい。」
必死の思いをぶつけてみたが、
答えは無情にもダメだった。
全部買ってもらえることをいいことに、
「更なる品質の向上」、
「販売していくための努力」が
置き去りになっていた。
そして、茂木社長の言葉には、
「あらゆる努力を重ねることが、品質を守り、
下仁田納豆を本物に育てることなのだ。」
というメッセージが秘められていた。
それから、意を決して東京の有名百貨店、
デパートへ売り込みに足を運んだ。
驚くことに、営業に行く先々で
待ち構えたように注文を頂いた。
サンプルを評価することもなく、
値段も提示する前に。
有名百貨店のバイヤーはそっと教えてくれた。
茂木社長がこっそりと
サンプルを送り続けてくれていたことを。
そして、それは一件だけでなく、
すべての有名店に、
しかも定期的にずっと送ってくれていたことを。
これまでの茂木社長とのやり取りが
頭の中で蘇ってくる、
自分の愚かさ、人のぬくもり、
そして茂木社長への感謝、
様々な感情の重なりに、
自然と涙が溢れて止まらない。
そこからは今まで以上に納豆が売れた。
そして、下仁田納豆は独り立ちした。
数年前、茂木社長はお亡くなりになられた。
これまでに頂いた教えやご恩を
まだまだ返していないのに・・・。
茂木社長は言っていた。
「いずれまた、君のところに
食を目指す若者が来たら、
同じようにしてやってくれ。
ものは順繰り。私もそうだったのだから・・・。」
人目をはばかることなく号泣した。
心に空いた大きな穴、
埋めるように本物の納豆を造り続けたい。
茂木社長への感謝と共に。
「今日はマシンガントークで
しゃべり続けましたが大丈夫でしたか?」
南都さんはにっこりと笑う。
こだわり続けた製法や品質も、
ここまで続けてこれたこともすべて、
納豆を通じて出会った人のおかげ。
「自分はそんな立派な人間じゃない。」
一言では伝えきることはできないが、
これが下仁田納豆の原点なのだと。
ただ、そのことを伝えるための
マシンガントーク。
ありのまま、等身大の南都さん。
納豆は一粒の豆が時間を掛けて、
たくさんの微生物の働きによって発酵し、
連鎖的に美味しくなっていく。
人と人もそのようになれたなら。
南都さんご夫妻の秘めた想い。
そんな願いは、ネバネバ糸となって、
切っても切っても、いつまでもいつまでも、
ネバネバと伸び続けてゆくのでした。
めでたしめでたし。



南都さんの父親が、
回り道をしながらも家族10人を養っていくための手段として
「納豆屋」を始めた。

当時は造った納豆を売り歩く、
引き売りの納豆屋だった。
「なっとぉ、なっとぉ~~♪」と売り歩く
父の姿の頼もしさは、当たり前でもあり、
思春期を経て、少しづつ
「自分はもっと大きな仕事がしたい。」
そう考えるようになっていったという。
高専を卒業し社会に出て、
設計エンジニアとして働くことになった。
社会に出て都会での生活は
何かをすり減らしていくようだった。
そして、時々思い出す父親の作る納豆が
懐かしくも、美味しくも感じるようになってきた。
そんな時、突然、父が家族に廃業を告げた。
「苦しいながらもなんとか子供達が育ってくれた。
これでもう納豆屋には未練がない。」
何かにこだわって
造ってきたわけではないだろうが、
それでもおいしい父親の納豆。
それ以上考えることもないまま、
自分の居場所を探すように「継がせてほしい。」と
自然に結論を出していた。
父、母、自分の3人が食べていけるように、
引き売りからスーパーへの卸を
増やしていくことを考えた。
電話帳を片手に片っ端から営業を掛けた。
ほとんど、すべてのスーパーで断られた。
その理由はすべて「値段が高い。」ということだった。
納豆業界もオートメーション化が進んでいた。
炭火を使って発酵させる。
寝ずに番をして造る納豆は
当然価格では太刀打ちできない。
絶望の中、それでも価格を合わせるか、
首をつる覚悟で考えていた。
そんな時に救いの神が現れた。
もぎ豆腐店の茂木稔社長との出会いだ。
値段よりも品質に興味を持ってくれた。
そして初めて試食をしてくれた。
「なかなかいい。どんな大豆を使っているか?」
原材料を聞かれた。
「大豆は一番安いものを問屋から買っている。
国産か外国産かも分からない。
でも、技術があるから、
うちの納豆はおいしいと言ってもらっている。」
と答えた。
当時の南都さんは素材など興味がなかった。
生きるために造ってきた納豆を
如何にして売っていくか。
商売とはそういうものだと理解していた。
茂木社長は言う。

「食べるもののおいしさは
素材の良さを引き出してこそ。
素材7割、製法3割だ。
いい素材で造れ。全部買ってやる。」
すべてのフレーズに衝撃を受けた。
「この人に付いていくしかない!」
素直にそう思った。
茂木社長に買ってもらえるように、
いい素材で造った。

そして、
本当に全部買ってもらえるようになった。
ただの納豆屋から、
「本当にいい納豆とは」という命題を持つ
本物の納豆屋へ変革していくための
衝撃的な教えだった。
さらにドラマは続く。
一年して、
茂木社長から取引の停止を言い渡された。
理由は「君は努力を何もしていない。」
と言うことだった。
まったく意味が理解できないまま、
茂木社長に詰め寄った。
「取引を停止されたら売り先がない。
店がつぶれてしまう。なんとかしてほしい。」
必死の思いをぶつけてみたが、
答えは無情にもダメだった。
全部買ってもらえることをいいことに、
「更なる品質の向上」、
「販売していくための努力」が
置き去りになっていた。
そして、茂木社長の言葉には、
「あらゆる努力を重ねることが、品質を守り、
下仁田納豆を本物に育てることなのだ。」
というメッセージが秘められていた。
それから、意を決して東京の有名百貨店、
デパートへ売り込みに足を運んだ。
驚くことに、営業に行く先々で
待ち構えたように注文を頂いた。
サンプルを評価することもなく、
値段も提示する前に。
有名百貨店のバイヤーはそっと教えてくれた。
茂木社長がこっそりと
サンプルを送り続けてくれていたことを。
そして、それは一件だけでなく、
すべての有名店に、
しかも定期的にずっと送ってくれていたことを。
これまでの茂木社長とのやり取りが
頭の中で蘇ってくる、
自分の愚かさ、人のぬくもり、
そして茂木社長への感謝、
様々な感情の重なりに、
自然と涙が溢れて止まらない。
そこからは今まで以上に納豆が売れた。
そして、下仁田納豆は独り立ちした。
数年前、茂木社長はお亡くなりになられた。
これまでに頂いた教えやご恩を
まだまだ返していないのに・・・。
茂木社長は言っていた。
「いずれまた、君のところに
食を目指す若者が来たら、
同じようにしてやってくれ。
ものは順繰り。私もそうだったのだから・・・。」
人目をはばかることなく号泣した。
心に空いた大きな穴、
埋めるように本物の納豆を造り続けたい。
茂木社長への感謝と共に。
「今日はマシンガントークで
しゃべり続けましたが大丈夫でしたか?」
南都さんはにっこりと笑う。
こだわり続けた製法や品質も、
ここまで続けてこれたこともすべて、
納豆を通じて出会った人のおかげ。
「自分はそんな立派な人間じゃない。」
一言では伝えきることはできないが、
これが下仁田納豆の原点なのだと。
ただ、そのことを伝えるための
マシンガントーク。
ありのまま、等身大の南都さん。
納豆は一粒の豆が時間を掛けて、
たくさんの微生物の働きによって発酵し、
連鎖的に美味しくなっていく。
人と人もそのようになれたなら。
南都さんご夫妻の秘めた想い。
そんな願いは、ネバネバ糸となって、
切っても切っても、いつまでもいつまでも、
ネバネバと伸び続けてゆくのでした。
めでたしめでたし。



※会員のみコメントを受け付けております、ログインが必要です。